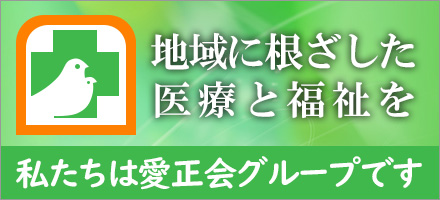『紙芝居』
グループ活動の時間に紙芝居を行った様子をご紹介いたします。
昭和初期、紙芝居を見る時には駄菓子を買う決まりがあり、水飴をこね回し、1番白くできた子供には景品がもらえたそうです。
駄菓子は水飴が多かったようですが、今回の紙芝居ではきな粉飴とマシュマロをこちらでご用意しました。
みなさんにまずどちらかお好きな方のおやつを選んでいただき、その後くじを引いてもらって、当たったらもう一つおやつがもらえるというやり方をすることで、昔の雰囲気を思い出していただき、楽しんでいただきました。
この日の紙芝居は、「昭和の窓」と「さらやしきのおきく」の2本立てで行いました。

紙芝居のはじまりはじまり!!お好きな方の駄菓子をどうぞ🤲


割りばしで作ったくじ引きです‼️当たりが出たら、もう1個もらえますよ~😊
1本目は、「昭和の窓」という紙芝居です‼️

表紙の絵の真ん中に四角い穴があいており、1枚ずつめくると、ここに、「マッチ」「かまど」「炊飯器」などの昔日常的に使用していたものが絵で出てきます。「これは何でしょうか?」の職員の問いかけに皆さん答えていただき、使い方など昔の話を聞かせていただきました。
2本目は、夏にちなんで幽霊が出てくる「さらやしきのおきく」という紙芝居です‼️


大切なお皿を1枚なくしたといって、屋敷の主人によって、井戸に投げ込まれたおきくは幽霊になりました。その幽霊を見ようと、見物人まで出るようになって・・・


井戸から出てきたおきくは「うらめしい。1まーい、2まーい・・・」
紙芝居に隠れていますが、感情を込めて一人ひとりの役になりきって演じる職員‼️